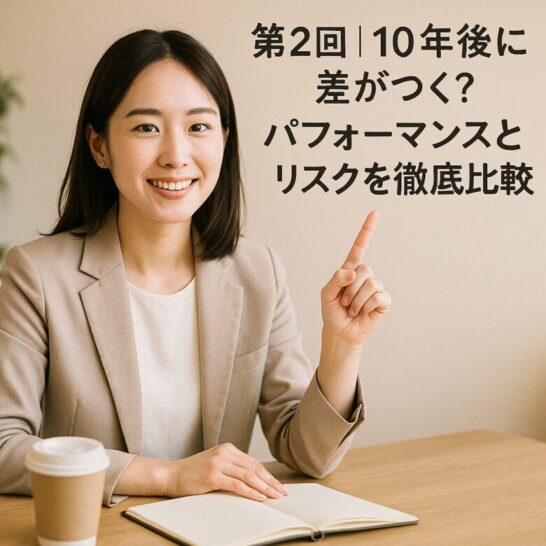
これから投資を始めたい20〜30代のあなたへ
「貯金はある程度できたけど、そろそろ資産運用も考えたほうがいいのかな」
そんなふうに思い始めたあなたに向けて、この記事を書きました。
いざ投資について調べ始めると、
「インデックス投資」「アクティブ投資」など、専門用語がたくさん出てきて戸惑うかもしれません。
でも大丈夫。
ここでは、これから初めて資産運用をスタートする人に向けて、
インデックス投資とアクティブ投資の違いを、わかりやすく整理してお伝えします。
自分に合った運用スタイルを見つける参考にしてみてくださいね。
第1回はこちら
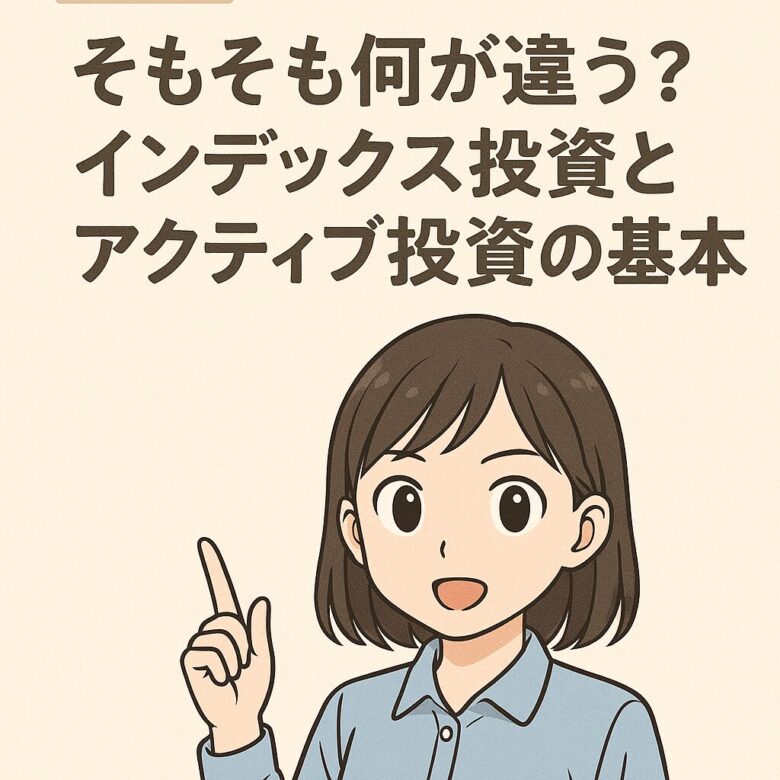
なぜインデックス投資は「勝ちやすい」と言われるのか?
前回の記事では、インデックス投資とアクティブ投資の基本的な違いを解説しました。 今回は、実際に「10年間運用した場合、どちらが有利なのか?」という視点から、パフォーマンスとリスクの違いを比較していきます。
結論から言うと、長期投資ではインデックス投資が勝ちやすいというデータが多数あります。 ただし、それは「必ずインデックスが勝つ」という意味ではありません。一部のアクティブファンドはインデックスを上回る成果を出しており、選び方次第で十分チャンスもあります。
1. 過去10年のリターン比較:インデックス vs アクティブ
過去10年の投資成績を見ると、インデックスファンドの多くが安定した成績を残しています。
たとえば、米S&P500に連動するインデックスファンドは、2013年〜2022年の10年間で年平均約10%のリターンを記録しています。
一方、同期間のアクティブファンド全体の平均リターンはこれを下回っており、 7〜8割以上のアクティブファンドがインデックスに負けているという調査結果も出ています(出典:SPIVAスコアカード)。
これは日本のファンドにも当てはまり、TOPIX連動型インデックスに対し、多くの国内株アクティブファンドが下回る傾向があります。
📌 補足:SPIVA(スパイバ)とは?
S&P社が毎年発表している、アクティブファンドとインデックスファンドの成績比較レポート。
- 日本株、米国株、グローバル株など、複数のカテゴリーで分析
- アクティブファンドの大半がインデックスに勝てていないことを示している
👉 詳細はこちら:SPIVA公式サイト(日本語)
2. 長期投資における「コスト」の影響は想像以上に大きい
インデックス投資が強い理由のひとつが、運用コストの安さです。
たとえば、代表的な低コストインデックスファンドである「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の信託報酬は年0.1133%(税込、2025年4月時点)と非常に低水準で、長期投資におけるコスト負担を最小限に抑えられます。
インデックスファンドの信託報酬は一般的に年0.1%〜0.3%程度が多く、 一方のアクティブファンドは年1〜2%前後と、コスト面で明確な差があります。
この1%前後の差は、複利の力によって長期で大きな違いになります。
たとえば、100万円を年利5%で20年間運用した場合、以下のような差が出ます:
- 信託報酬0.1133%(eMAXIS Slim 全世界株式):約271万円に成長
- 信託報酬1.5%:約220万円にしかならない
このように、「何に投資するか」だけでなく、「どれだけコストがかかるか」も投資成果に大きく影響するのです。
3. アクティブファンドにもチャンスはある!成功例と特徴
ここまでインデックス有利の話をしてきましたが、 アクティブファンドの中には長期的にインデックスを上回る成果を出している例も存在します。
✅ 代表的な成功ファンドの例:
- ひふみ投信:独自調査に基づく銘柄選定で、高いリターンを記録。信託報酬は年1.078%(税込、2025年4月時点)。
- コモンズ30ファンド:30年後も続く企業への長期投資で着実に成長。信託報酬は年1.078%(税込、2025年4月時点)。
- ARK Innovation ETF(米国):破壊的イノベーション企業に集中投資して注目を集めた。信託報酬は年0.75%(2025年4月時点)。なお、日本国内では直接購入することは難しく、海外ETF取扱の証券会社を通じて買い付ける必要があります。
これらのファンドに共通しているのは:
- 明確な投資哲学がある
- 情報発信が透明で信頼しやすい
- ファンドマネージャーの顔が見える
ただし、過去に勝ったファンドが今後も勝ち続ける保証はないことにも注意が必要です。 アクティブ投資を選ぶなら、「なぜそのファンドを選ぶのか」を自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。
4. 駄目なアクティブファンドの典型例:タコ足配当ファンドに注意
アクティブファンドの中には、投資家受けする配当利回りだけを強調し、その実態は“元本を切り崩して配当を出す”タコ足配当型ファンドも存在します。
たとえば過去に話題となった「グローバル・ソブリン・オープン(通称:グロソブ)」は、配当の原資の多くを運用益ではなく元本から取り崩しており、基準価額が右肩下がりであるにもかかわらず、毎月一定額の分配金を出し続けていました。
このようなファンドでは、長期保有しても資産が目減りする可能性が高く、「配当をもらっているのに、残高が減っていく」という現象が起きます。
さらに悪化すると、運用資産の減少によりファンドの規模が縮小し、最終的には繰上償還(投信の強制終了)に至るケースもあります。繰上償還が行われると、意図しないタイミングでの資産回収を強いられ、長期の資産形成に支障が出る恐れがあります。
❌ 注意すべきポイント:
- 分配金が高すぎる(年10%超など)
- 基準価額が継続的に下落している
- 毎月分配型で分配の原資に明確な説明がない
高配当をうたうファンドでも、「その配当はどこから来ているのか?」を見極めることが大切です。 真に健全なアクティブファンドは、資産を増やしながら適正な分配を行うことを目指しています。
5. リスク(値動き)の違いは?
一般的に、インデックスファンドは「市場全体」に分散投資しているため、個別株よりはリスクが抑えられる傾向があります。
ただし、「値動きが穏やか」とは限りません。インデックスファンドは市場全体に連動するため、相場が大きく下落する局面では、インデックスファンドも一緒に大きく下がるリスクがあります。
一方、アクティブファンドは、特定の業種やテーマに集中することが多く、個別銘柄の影響を強く受けやすいため、値動きが激しくなる(=ハイリスク・ハイリターン)傾向があります。
つまり、どちらの投資スタイルでも値動きによる感情の揺れは避けられない面がありますが、
- 値動きの背景がわかりやすく、全体の動きとして納得しやすい → インデックス
- 銘柄やテーマへの思い入れが強く、リスクを取ってでも高リターンを狙いたい → アクティブ
というように、自分のリスク許容度や投資目的に合わせて選ぶのが重要です。
6. 平均回帰(Mean Reversion)の罠:アクティブファンドの“一発屋”問題
アクティブファンドの成績を見て「過去に好成績だったから買ってみよう」と思う人も多いですが、実はこれが最も陥りやすいワナの一つです。
ファンドの運用成績は年ごとに変動します。ある年に好調だったファンドが翌年もそのまま好調である保証はなく、むしろ「平均に戻っていく=平均回帰」の傾向があります。
たとえば、2020年に爆発的なリターンを記録したARK Innovation ETFは、翌年から大きく下落し、2022年にはピークから約7割の価値を失いました。
一方、インデックスファンドは市場全体に連動するという特性上、経済が成長すればリターンも伸びやすいですが、市場そのものが長期間低迷すれば当然リターンもふるいません。つまり、「長く負けない」とは限らず、市場環境次第で厳しい局面もあることを理解しておく必要があります。
つまり、短期的な好成績に飛びついて投資をするのは危険です。アクティブファンドは「光る年」がある一方で、その裏には不調な年も含まれていることを前提にすべきです。
また、インデックスファンドについても万能ではなく、市場全体に連動する性質上、リターンは市場の成長に依存します。市場が長期間低迷すればリターンも低くなるため、「放っておけば必ず報われる」という保証があるわけではありません。インデックス投資も“市場リスク”を受ける投資手法であることを理解しておく必要があります。
7. 資金流入とパフォーマンスの逆相関:「人気化した時には遅い」問題
特にアクティブファンドは、人気が出るほどパフォーマンスが下がりやすくなるという特徴があります。
理由は:
- 資金流入によって運用対象の銘柄数が増え、本来得意だった小型株などへの集中が難しくなる
- ファンドマネージャーの投資判断が「大量の資金」によって制約を受けるようになる
これはグロソブでも見られた現象で、「投資家の人気が最も高いとき=ピークアウトの兆し」となり、そこから基準価額が下がっていくという典型例となりました。
アクティブファンドを選ぶときは、「今話題のファンド」ではなく、運用残高や資金流入の勢いも冷静に見極めることが大切です。
まとめ:最初の一歩は、シンプルに踏み出そう
投資にはいろいろなスタイルがありますが、これから初めて資産運用を始めるなら、まずはインデックス投資からチャレンジしてみるのがおすすめです。
手間がかからず、コストも低く、長期的にじっくり資産を育てることができる。
「よくわからないけど、やってみたい」という人にもぴったりの選択肢です。
大切なのは、完璧なスタートを目指すことではなく、まず一歩を踏み出すこと。
小さな積み重ねが、将来のあなたを支えてくれるはずです。
さあ、今日からあなたも資産運用の一歩を踏み出してみましょう!
次回はいよいよ最終回。 第3回|あなたにぴったりの投資スタイル診断では、あなたに合った投資スタイルを見つけるための診断ロジックや選び方のフローチャートをご紹介します。
「インデックス?アクティブ? 結局どっちが自分向き?」と迷っている方は、ぜひチェックしてみてください。

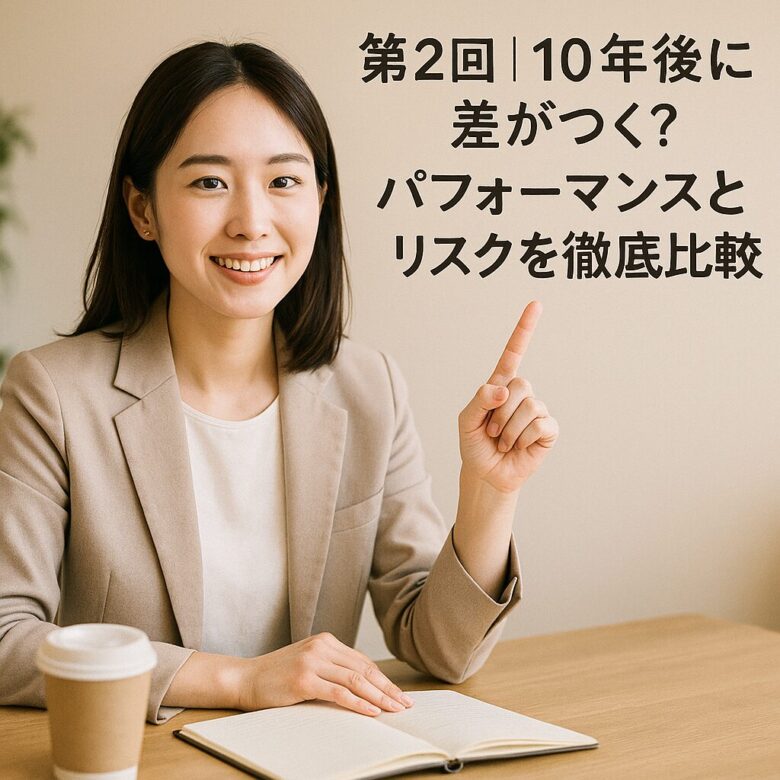


コメント