
🔰 「国民1人あたり1000万円の借金」は本当?
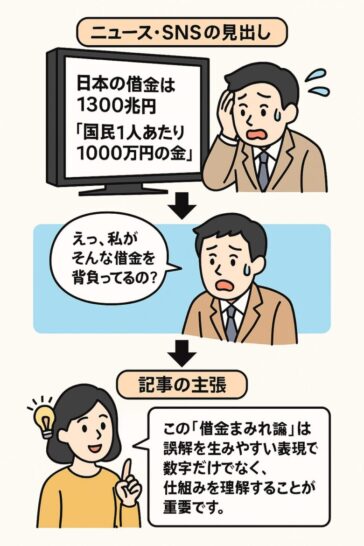
ニュースやSNSでよく見かける「日本の借金は1300兆円」「国民1人あたり1000万円の借金」。
これを見るたびに、不安を感じたことはありませんか?
「えっ、私がそんな借金背負ってるの?」と思ってしまいそうですよね。
でも、まずは冷静に考えてみましょう。
🔵 実はこの「借金まみれ論」、かなり誤解を生みやすい表現なんです。
今回は、そんな「国の借金」の正体について、初めての方にもわかりやすくお伝えします。
✅ なぜ「借金=破綻」ではないのか?
【1】国の借金は“誰かの資産”である
「国の借金」とは、主に政府が発行する国債のこと。
これは「お金を借りている証書」のようなもので、政府はこの国債を売ってお金を調達し、公共サービスや社会保障、景気対策などに使います。
では、この国債を誰が買っているのか?
- 銀行(預金の運用先)
- 生命保険・損保などの機関投資家
- 年金機構(GPIF)
- 日銀(日本銀行)
- 一部の個人投資家
つまり、国債という“政府の負債”は、誰かにとっての「資産」なのです。
💡 財政赤字=民間の黒字
これはマクロ経済における基本的な関係です。
たとえば、あなたが銀行に預けているお金は、その銀行が国債として運用している可能性もある。つまり、国の借金があるから、民間にお金が流れているという側面があるんです。
【2】日本政府は“自国通貨建て”で借金している
🔑 日本政府の借金は「円建て」。つまり、返済も円でできる。
世界には、「国の借金が返せずにデフォルト(債務不履行)」になった国もあります。でもそれらの多くは、ドルやユーロなど、外国通貨で借金していたことが原因でした。
例えばギリシャやアルゼンチンは、自国通貨ではなく、ユーロやドル建てで債務を抱え、通貨発行ができず、資金繰りに行き詰まりました。
一方で日本は、「円」を発行できる唯一の存在。必要ならば、通貨の供給が可能です。
💬 よくある誤解:
「いくらでもお金を刷ったらハイパーインフレになるんじゃ?」
たしかに、過剰な通貨発行はインフレを招きます。
でも今の日本はどうでしょうか?
- 過去30年、ほとんどが低インフレかデフレ傾向
- 物価上昇があっても、賃金が追いつかない「スタグフレーション型」
- 金利は世界最低水準を長年維持
つまり、現時点で「お金を刷りすぎている」状況とは真逆。
むしろ、お金が足りていないのでは?という状況です。
【3】国債は“返す”ものではなく“回す”もの
「1300兆円も借金がある!全部返せるの?」という疑問もよく聞きますが…
実は、国債はほぼ常に“借り換え”で運用されているのが実態です。
これを「ロールオーバー」と言い、国債の満期が来たら、新しい国債を発行して支払いに充てています。つまり、借金は回しながら経済を動かす“仕組みの一部”になっているんです。
しかも、現在では日銀が国債の4割以上を保有しています。
つまり、政府が発行した国債を、政府の“子会社”のような日銀が持っているという構図も含まれているのです。
【4】政府の赤字=経済への血液循環
ここが一番大事かもしれません。
「借金は悪いこと」というイメージがありますが、経済の仕組みで見ればそれは一面的。国の借金は、民間へのお金の供給手段でもあります。
📊 政府が赤字を出して支出する
→ 民間の所得になる
→ 消費・投資に回る
→ 経済が動く
この流れが、「財政乗数効果」と呼ばれるメカニズムです。
たとえば、公共事業で道路を整備すれば、建設会社や労働者にお金が渡り、消費が活発になります。育児支援や医療費補助に使えば、家計にゆとりができ、将来不安も和らぎます。
つまり、赤字は悪ではなく、「どのように使うか」が問われる時代に入っているんです。
🔍 では、なぜ「破綻する」という人がいるのか?
テレビや新聞ではよく「このままでは財政破綻」と語られます。
その主な根拠は以下のようなものです:
- 借金は返さなければならないという“常識”
- 金利が上がれば利払いで財政が持たなくなる
- 子や孫にツケを回す無責任な政治
でも、これらは多くの場合、「家計簿感覚で国を語っている」ことが原因です。
📌 政府は家計と違い、自国通貨を発行できる存在です。
返済不能になるリスクは極めて限定的。
問題があるとすれば、使い道の質やインフレとのバランスです。
✅ 結論|「国の借金=危機」ではなく、「どう使うか」が重要
- 借金の総額だけを見て不安になる必要はない
- 国債は民間の資産でもあり、経済の血流を生む道具
- 破綻するかどうかよりも、「どんな経済と社会を作るか」が本質的な問い
💬「国の借金は怖い」と思っていたあなたへ――
数字だけでは見えない“仕組み”を知ることで、不安ではなく「考える力」に変えていけます。
🔜 次回予告
第2回|なぜ借金がここまで増えたの?戦後から現代への財政の歩み

コメント